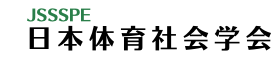日時
日時 2025年6月22日(日)14:20~16:45
場所 東北大学川内南キャンパス(文科系総合講義棟 2階 第1講義室(経済学部)203教室)
テーマ
「学び合い」で共生する体育授業を目指して:中学校と高等学校における体育授業の「男女共習」を考える
開催趣旨
2025年2月に開催した日本体育社会学会の研究セミナーは、「中学校と高等学校の体育授業における『男女共習』という理念と現状」というテーマで行われた。加藤凌先生は、体育科教育の立場から保健体育教師や生徒への調査結果に基づき、「男女共習」による体育授業を越えたより創造的な体育授業の必要性について報告した。つまり、中学校や高校の体育授業で「男女共習」が達成されれば問題が解決されるという単純な問題ではなく、体育授業の内容やあり方自体を生徒の個性に合わせて創造的に組み替える必要性を指摘された。このシンポジウムでは、研究セミナーで指摘された論点を踏まえ、体育授業における多様な生徒の「学び合い」という視点を通して共生する体育授業を創造する可能性について議論する。
コロナ禍の期間に全国の大学の授業はオンラインを通したオンデマンド型で行われることがあり、一部の大学ではその利点を評価してオンデマンド授業を現在も継続している。一定の知識を学習するという点ではオンデマンド型の授業で十分に学習を行うことができる。しかし、オンデマンド型の授業では、学生間が「学び合う」という教育の根幹に関わる活動が失われる。体育の授業は対面が基本であり、異なる性別、障がいの有無、体格、身体能力、競技経験などの異なる多様な他者と同じスポーツの技術の習得を通して学び合うことができる。このような視点で考えた時に、「男女別習」よりも「男女共習」による授業の方が多様な学び合いを実現できるだろう。このシンポジウムでは、「男女共習」を生徒が性別にかかわらず同じ教師から同じ場所で同じ学習内容を学ぶ授業形態を「男女共習」と広義に定義する。
シンポジウムでは、体育社会学者、体育科教育学者の立場からこの問題について講演を行う。体育社会学者はジェンダーの視点から「男女共習」授業が浸透しない理由や背景について講演する。体育科教育学者は、「男女共習」の体育授業を行う上での工夫や評価上の課題について報告する。
シンポジウムの後半では、参加者によるグループワークを通してこのテーマに関して発展的に議論を深めることを目指す。グループワークの目的は、参加者の体育授業に関する経験を理解し、「男女共習」の体育授業を行う上での工夫や研究のアイデアを共有することである。参加者は会場入場時にくじを引き、決められた席に座る。グループワークでは自己紹介をして、体育授業の「男女共習」や「男女別習」に関する自身の経験や指導上の工夫について話し合う。参加者は事前に送付するURLからグーグルフォームで自身の中学・高校・所属先での男女共習・男女別習の状況について回答する。シンポジウムの冒頭で結果を簡単に紹介する。
登壇者(敬称略)
三上 純(関西大学)
「共生社会のための男女共習」が意味すること
梅澤 秋久(横浜国立大学)
「学び合い」で共生する体育授業を目指して:体育科教育の立場から体育授業の「男女共習」を考える
【コーディネーター】
浅沼 道成(元岩手大学) 大沼 義彦(日本女子大学)
白石 翔 (富山大学) 千葉 直樹(中京大学)
【司会】
秋吉 遼子(東海大学)