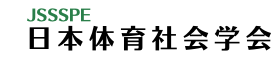会長挨拶
日本体育社会学会 会長
(一社)日本体育・スポーツ・健康学会
体育社会学専門領域 代表 高峰 修(明治大学)
本学会は(一社)日本体育・スポーツ・健康学会体育社会学専門領域を母体とする独立学会として2023年4月1日に創設されました。独立学会としての歴史はわずかですが、体育社会学専門領域の前身である体育社会学専門分科会は1962(昭和37)年に発足しており、60年以上の歴史をもちます。
体育社会学専門分科会は当時の日本体育学会で三番目に発足した専門分科会でした。その後、専門分科会という名称はすべて専門領域に変更され、現在では16の専門領域が日本体育・スポーツ・健康学会内で活動を展開しています。そしてそのうち半数を超える9の専門領域が、各専門領域と何らかの連携をするかたちで独立学会としても独自の活動を行なっています。このことは、専門化、細分化という日本の体育・スポーツ・健康科学の70余年における発展の一端を表しているといえるでしょう。
他方、日本体育・スポーツ・健康学会の大会プログラムは、応用(領域横断)研究部会が企画するテーマ別企画を中心に構成されるようになりました。こうした動向の背景には、専門化、細分化した研究成果を組み替え直して学際的、統合的な知の構築を目指す、さらにはそうした知を社会に還元していくといったねらいがあります。
このように、本学会は体育・スポーツ・健康科学が一方では拡大・分散し、他方では統合・協働するという両ベクトルが交差する磁場において誕生したことになります。
こうした状況においては、本学会は大きく分けて二つの課題を抱えているといえるでしょう。一つは、体育社会学としてのアイデンティティの探索です。ここにはさらに、体育・スポーツ・健康科学分野における体育社会学としてのアイデンティティ、そしてスポーツ社会学との関わりにおける体育社会学としてのアイデンティティの両側面があると思われます。
もう一つの課題は、他の専門領域(学会)との連携や協働です。現代社会における体育やスポーツをめぐる現象や構造の複雑化、規範や価値観等の変化を認識しつつ、体育やスポーツの研究のみならず「実践に寄与する」という本学会の目的の達成を見据えると、今や社会学という分野を超えて近接し関連する他分野との連携や協働は欠かせない状況にあると思われます。
“体育の日”が“スポーツの日”に、“国民体育大会”が“国民スポーツ大会”に換わったように、日本社会における体育がスポーツに置き換わりつつあります。しかし日本人のスポーツ観やスポーツに関する態度、行動の大部分は、“体育”の中で培われていると言っても過言ではないでしょう。そのような日本の“体育”へのまなざしや問いかけは、体育社会学だからこそ取り組めることなのかもしれません。このような問題意識をもちながら、本学会として社会に貢献できることを探っていきたいと考えています。本学会へのご支援、ご協力をお願い申し上げます。